【茨城県守谷市・龍ケ崎市】「自分のことは好きですか?」「はい!」と答える大人になってと願う松山理事長。運営5園はフラットで等身大
社会福祉法人山ゆり会 まつやま保育グループ
- 保育園
- 茨城県龍ケ崎市
- 茨城県守谷市
- 否定語禁止
- Iメッセージ
- 泥んこ遊び
- 等身大の園
- 本音で語り合えるチーム

松山理事長
理事長 松山圭一郎
1978年7月11日生。まつやま保育園、まつやま中央保育園、まつやま大宮保育園、まつやま松並保育園、まつやま百合ケ丘保育園の5つの園を運営する社会福祉法人山ゆり会の理事長。30歳の時、不動産業界から保育業界に転向。幼少期は、旗を持って走り回り、友達を引き連れていたそう。どこにいるのか分からなくなってしまうからと、母親に鈴をつけられるほどの活発さ。当時住んでいた団地には鈴の音を轟かせていた。最近の休日は、子どもたちのバスケのおっかけに勤しんでいるそう。
目次
「自分のことは好きですか?」
否定語禁止令
世界は学びで満ちている!
「言っていること」=「やっていること」
園長のチーム作り
やればできるのよ
「自分のことは好きですか?」
「全ての子どもの幸せを願っている。“全て”とは、世界中の子どもたちのことです」と語る松山理事長。
「でも、すぐに叶えられるものではない。まずは、自分たちの地域の中で何ができるのか?」と問い、保育に向き合っている。

園庭で遊ぶ子どもたち
松山理事長は“子育て”を
子どもが社会に出て、自分の力で
しっかり生きていけるように成長させることだと
定義する。
そのために必要なものが
“自己肯定感”である。
そう考えたきっかけが
「自分のことは好きですか?」という問いだ。
「自分のことは好きですか?」と問われ、
自信をもって「はい」と答えられる大人は
案外少ないものだ。
自分自身を認められない人は、
他者と比べて「自分なんて」という言葉を繰り返してしまう。
松山理事長は「自分自身の力で、しっかり生きていくためには、自分を認めないといけない」という。
自分には、その側面は足りていないけれど、
これはできるから大丈夫と、
思うことができるのも重要だ。
“自己肯定感”に目を付けた松山理事長も
過去には、
自身の学歴にコンプレックスを抱いていた。
大学の推薦を得るほど
一生懸命に取り組んでいた“野球”。
練習に明け暮れた日々の中、
勉強する間はなかった。
人のことを羨んだ時期もあったが、
社会人となり、仕事で結果を出せたときに
「やれば認めてもらえる」という
“自信”がわいてきたという。
この“自信”が
「人よりも努力することができる力につながっていく」
と松山理事長は教えてくれた。
否定語禁止令
保育において、
「子どもたちの“やりたいこと”が、当たり前に出てくるように」
を意識している山ゆり会。
2017年には、
「否定語禁止令」
を、保育士たちに発布した。
園児たちは家で
「はやく食べなさい!」
「歯磨きをしなさい!」
などと言われているに違いない。
「家で言われていることを、保育園に来てまで言われていたら、子どもたちは疲れてしまう」と、松山理事長は考えた。
それからは、
「ダメ!」ではなく、
「~しようね」を使うよう呼びかけている。
例えば、廊下を走っている園児を見かけたとき、
「走っちゃダメ!」というのではなく、
「○○くんが怪我しちゃったら、先生悲しいよ」
とI(アイ)メッセージで伝える。

園児と遊ぶ先生
先生の想いは
どちらの声かけをする場合でも変わらない。
それならば、
より、園児たちに想いが伝わる届け方をしようと意識している。
禁止令の通達があったからといって
先生たちがすぐに声かけを変えられるわけではない。
しかし、「文化として否定語を使わないと、定着したことにより、否定語が目立つようになった」と説明する松山理事長。
その効果は、
先生同士のフォローがしやすくなるという結果にもつながった。

団らんする先生たち
否定語が聞こえたとき、
「●●先生、大丈夫?何かあったの?」
と、周りの先生が声をかけやすくなったという。
園児のための「否定語禁止令」は
先生たちにもいい影響をもたらしている。
世界は学びで満ちている!
文字や数字、色は“学び”である。
子どもたちの目に写る世界には、
耳に流れ込む音や言葉には、
どれほどの“学び”があふれているのだろう。
「どんぐりを10個あつめてみよう!」
1から10まで数える、これは算数の“学び”。
教室には、
自分やお友達の名前が書いてある物がいたるところに置いてある。
黒板を見ていなくても、
“学び”はいたるところに潜んでいるものだ。
山ゆり会の運営する保育園では
遊びを通して“学ぶこと”を促している。

園庭で遊ぶ園児たち
「小学校受験のない地域性にも、この考えが合っていたのだと思う」という松山理事長。
しかし、小学生になれば
授業が始まり、
1日中、椅子に座っておく必要がある。
椅子に座っておくにも体幹がなければ、
疲れてしまい、集中もできない。
もちろん、小学生に必要な体幹も
子どもたちは
力いっぱい遊ぶ中で身に着けていくのである。
算数、国語、美術に体育。
園児たちの世界は楽しい“学び”で満ちている。
「言っていること」=「やっていること」
山ゆり会のホームページを、ぜひ見てほしい。
園児と写る先生たちの姿はキラキラ輝いていて、
各保育園の外観はまるで、
一等地のモデルハウスのよう。

社会福祉法人山ゆり会が運営するまつやま保育園(茨城県守谷市本町)の外観
しかし、実際に保育園で働いている先生からは
「働く前と後で、ギャップがない」
という声が多く上がっている。
松山理事長にその秘訣を聞くと
「言っていることと、やっていることを一致させるだけです」
という。
ミスマッチは
「言っていること」と「やっていること」
が一致していない時に発生し、
離職や保護者の満足度の低下を引き起こす。
あくまで、等身大でいることが大切なのである。
「よく気にされる先生同士の人間関係も、価値観は人それぞれ」と話す松山理事長。
求職者に質問されるときも
「いいとは思うけど、いいと思うものはそれぞれ違うからね」と答えているそう。
そんな山ゆり会では、
求職者が実際に園に来て、先生たちと一緒に
保育をする日を設けている。

園舎内で遊ぶ園児たち
1日の体験が終わったのち、松山理事長が
現場の先生に、一つ質問する。
「一緒に働きたい?」
たったそれだけだが、
それが1番大切な気持ちであることは
間違いない。
入園を検討している保護者に見せるのも、
等身大の山ゆり会。
「保護者には三つ確認します」
1.うちは怪我が多いです
2.汚れることも多いです
3.子どもたちの自由な活動を大切にするため、発表会などの行事が少なくてつまらないです

泥だらけになって遊ぶ園児
「そういう保育園を求めていた!」
という、先生や保護者が集まった空間が
山ゆり会の保育園なのである。
園長のチーム作り
松山理事長は「先生たちが自由に楽しく、前向きに働けることを大切にしたい」と語る。
運営する5つの園は
フラットな関係であることが大切という。
もしも、5つの園がそれぞれ別の独自性を持っていたら、
法人としてのバランスを保つことはできないのである。
「あの園ではこうしてくれたのに!」と、
同じ山ゆり会の保育園の中で、優劣をつける結果となるからだ。
バランスを保った運営をしていくため、
松山理事長は外部の講師を招き、
1年間のチームビルディングを行った。
各園のトップである
園長同士を本音で語り合えるチームにしたのだ。

休憩時間に団らんする先生たち
その結果、園長同士が年齢や経歴に関わらず、
同じ立場で意見を交わしあえる環境が整っている。
そんな松山理事長は
「判断と責任だけ取るのが自分の立場」だという。
先生たちが、“自由”に“楽しく”、“前向き”に働けるように。
このようにして築かれた環境では
人が、新たな人を呼ぶ。
園には、親子で働いている人がいたり、
義妹と一緒に働いている人がいたり、
結婚を機に退職する先生が、後任を紹介したり、
元保護者や現保護者であったりと、
約3割が先生たちからの紹介や保護者等、
園と関わりのある人だという。
これは、山ゆり会の保育園が
大切な人に薦めたいと思える職場であることの
証明であろう。
やればできるのよ
「『あなたはやればできるのよ』と言われて育ってきました」
母親や学校の先生など
松山理事長が子どもの頃に出会った
多くの大人たちにかけてもらった言葉だという。
「もし、『あなたは本当にダメね』と言われていたら、僕はダメな人だと思い込んでいたと思う」と当時を振り返る。
幼少期から大学まで野球に打ち込んでいた
松山理事長は大学を卒業後、
都内で不動産業に就職した。
30歳になった、2009年の正月。
実家に帰った松山理事長に、
山ゆり会の創設者である母親が
「園の経営を、手伝ってくれないか?」と聞いた。
「当時、もうすぐ子どもも生まれるというところで…。その時、働いていた会社での地位も上がってきて、給料も大幅に下がるし…と、葛藤はありました」
という松山理事長。
しかし、目の前の母の姿が、
疲れているように見えた。
「助けないといけないと、感じました」
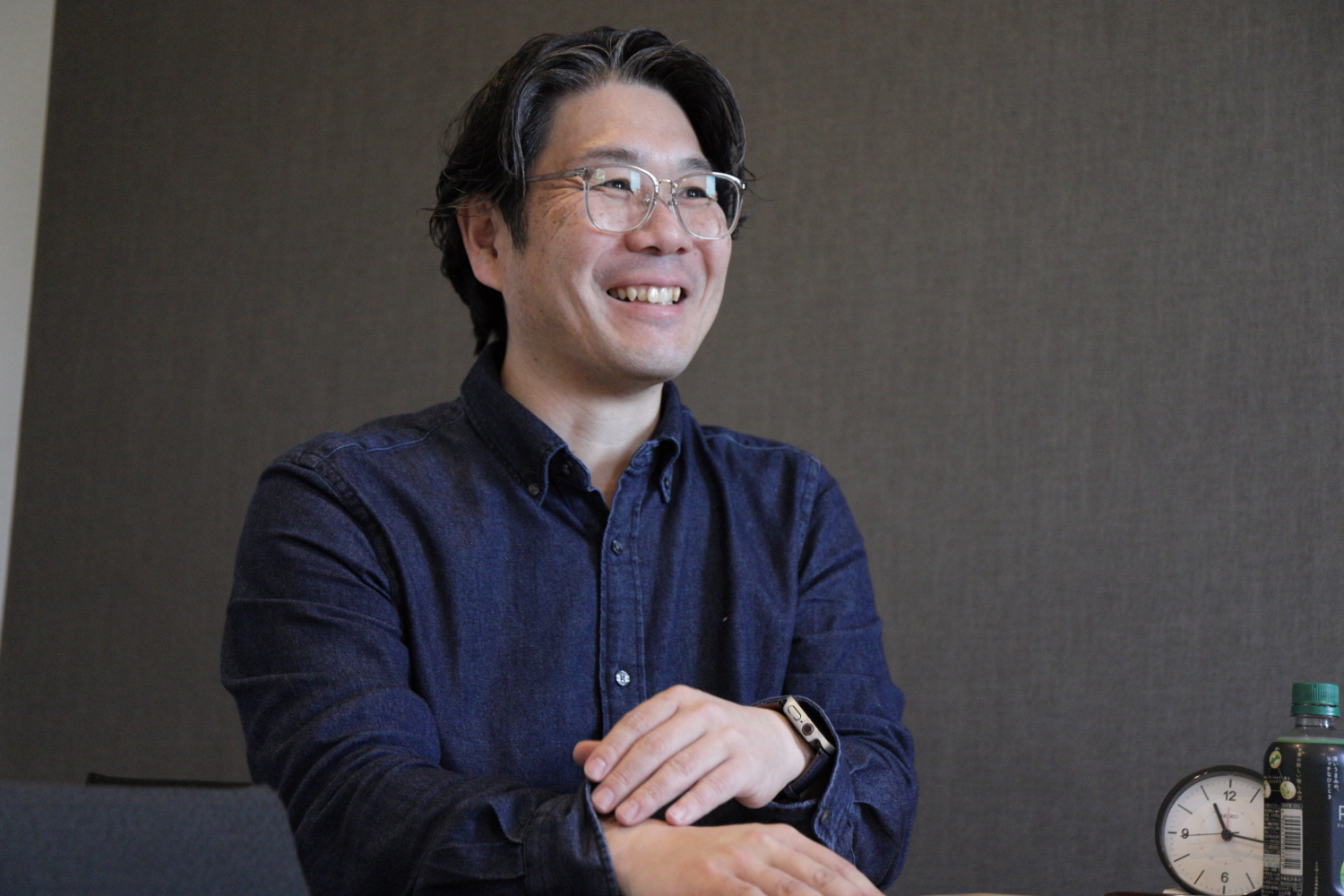
保育に携わり、表情が柔らかくなったといわれる松山理事長
山ゆり会を継ぐ決意を決めた
松山理事長は今、
「結果的に子育てにも参加できてよかった。前の会社の人と会うと、『表情が柔らくなって、顔が変わったな!』って言われるんです」と、穏やかに笑っていた。



